【なぜ筋肉は加齢で減るのか?】サルコペニアの原因と予防を解説
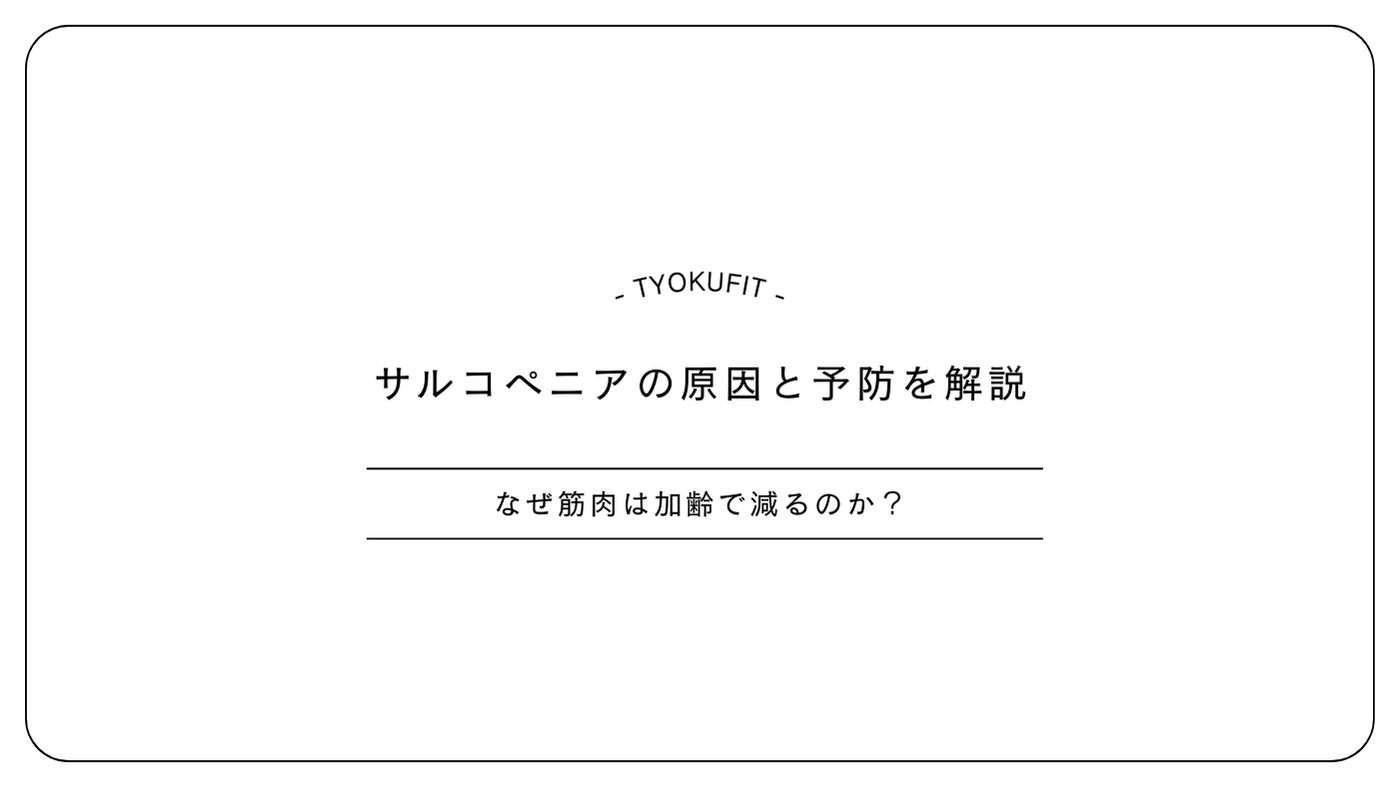
こんにちは。阪神尼崎駅から徒歩5分のパーソナルジムTYOKUFIT代表の樋口です。
「歳を取ると筋肉が落ちるのは当たり前」と思っていませんか?
確かに加齢とともに筋力や体力が低下していくのは自然な流れのように感じますが、その“筋肉の衰え”には予防可能な部分が多く含まれていることをご存知でしょうか?
今回のテーマは
加齢性筋肉減少=サルコペニア(Sarcopenia)。
その原因と予防法をトレーナーとしての現場経験と研究をもとに解説していきます。
サルコペニアとは?|“筋肉が失われていく”という意味
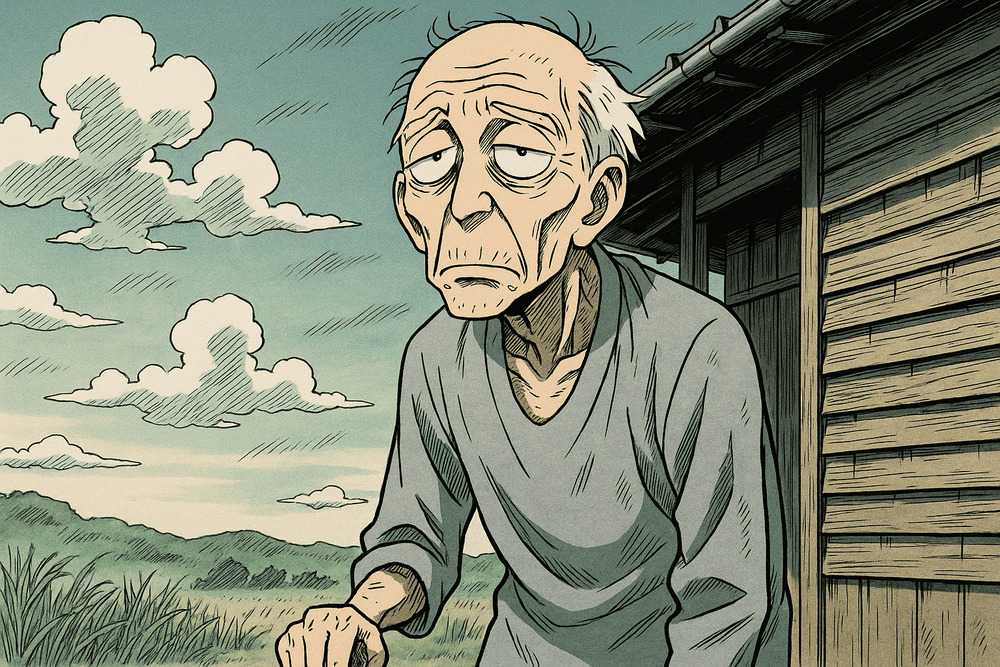
サルコペニアという言葉はギリシャ語の
sarx(肉・筋肉)penia(喪失・欠乏)
を組み合わせたもので、直訳すると「筋肉の喪失」という意味になります。
この言葉が医学的に使われるようになったのは1980年代後半以降で、現在では加齢とともに筋肉量・筋力・身体機能が低下していく状態を総称する用語として広く使われています。
欧州老年医学会(EWGSOP2, 2018)の診断基準では、以下の3つが評価指標とされます
- 筋力の低下(握力、椅子立ち上がりなど)
- 筋肉量の減少(体組成計、DXAなどで測定)
- 身体機能の低下(歩行速度など)
単に「筋肉が落ちた」というよりも、“動く力”や“生活機能”そのものが衰えていく進行性の状態がサルコペニアです。
なぜ年齢とともに筋肉は減るのか?|3つの科学的原因

サルコペニアの進行には、以下の3つのメカニズムが大きく関係しています。
① アナボリックレジスタンス(筋肉合成の感受性低下)
加齢によって筋肉の合成を促すシグナル(主にmTOR経路など)に対する反応が鈍くなる現象を「アナボリックレジスタンス」と呼びます。
この状態では、筋トレやたんぱく質の摂取といった筋肉にとっての刺激が、若い頃よりも効きづらくなるため、意識して行動しなければ筋量は徐々に減っていきます【Breen & Phillips, 2011】。
② 速筋線維(Type II)の選択的な減少と脱神経
人の筋肉には「遅筋(Type I)」と「速筋(Type II)」がありますが、加齢とともに特に速筋線維が萎縮・消失しやすいことがわかっています。
1988年のLexellらの研究では、80代の高齢者では若年者と比べて速筋線維が50%以上減少している例も確認されています。
また、加齢により筋肉を動かす神経そのものの数も減るため、筋線維が“使われず”に消えていく脱神経が進行し、動作のキレや反応速度が大きく低下していくのです【Narici & Maffulli, 2010】。
③ 身体活動量の減少
加齢に伴い、買い物・家事・外出といった日常の動きは少なくなります。
例えば
- 階段を上る
- 掃除や料理をする
- 歩いて移動する
といった “こまめな動作の積み重ね” は、筋肉や代謝を維持する大切な刺激です。
しかし、これらが減ることで筋肉は使われなくなり、身体は「もう必要ない」と判断して萎縮が進行してしまいます。
実際に健康な高齢者が わずか10日間ベッドで安静に過ごすだけで筋力や機能が大きく低下した という研究もあります【Kortebein et al., 2007】。
進行するとどうなる?|日常生活への悪影響
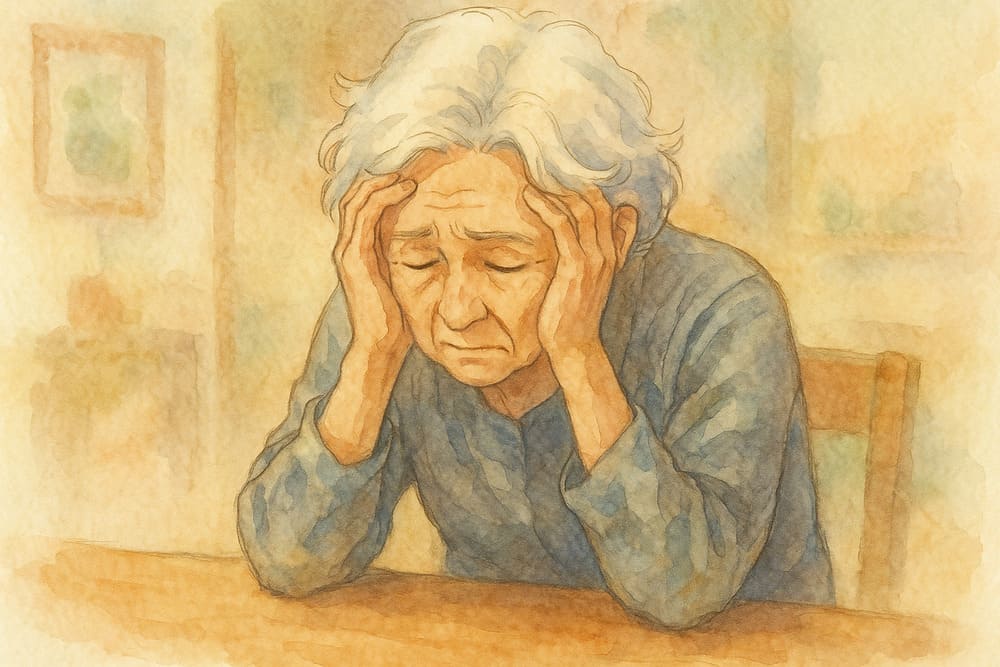
サルコペニアが進むと以下のようなリスクが高まります
- 歩くのが遅くなり外出が減る
- 疲れやすく動くことが面倒になる
- 転倒・骨折のリスクが上がる
- 代謝が低下して太りやすくなる
- 糖尿病高血圧など生活習慣病リスクが上がる
- 最終的には要介護状態になる可能性も
つまり筋肉は、見た目や体力の問題にとどまらず、健康寿命=自立した生活ができる期間を守るための“資産”だといえるのです。
サルコペニアを防ぐための3本柱
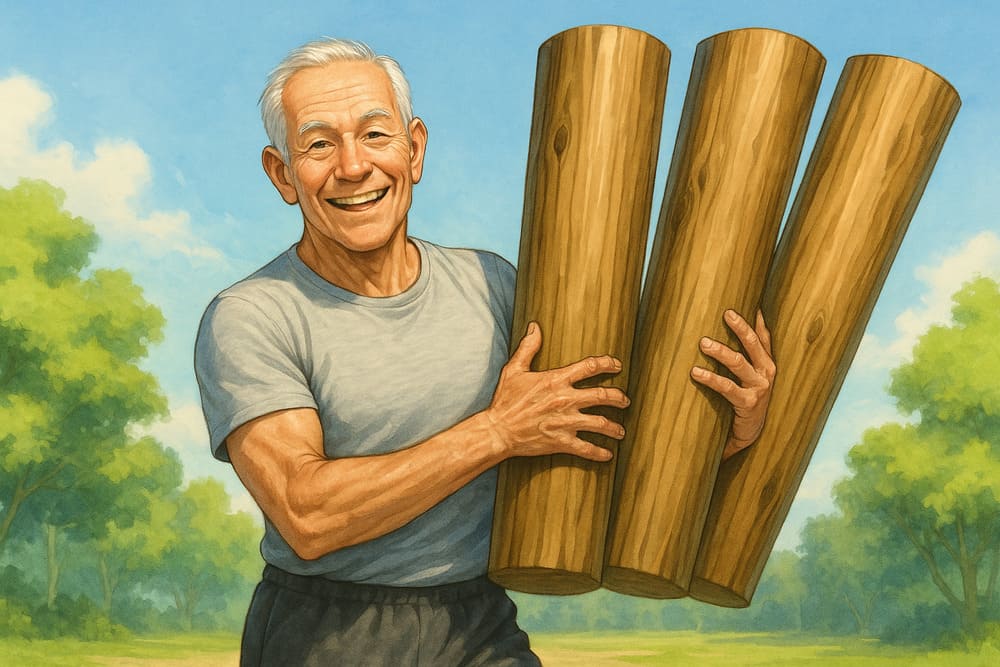
サルコペニアの進行を防ぐにはどうすればよいのでしょうか?研究で明らかになっている有効なアプローチは次の3つです。
① 筋トレ|最も確実な刺激
筋肉にとって一番の刺激は、やはりレジスタンストレーニング(筋トレ)です。
週2~3回の中~高強度の筋トレ(スクワット、ローイング、ヒップリフトなど)を継続することで筋肉量・筋力・神経系すべてが改善すると報告されています【Cruz-Jentoft et al., 2019】。
とくに重要なのが、下半身の大きな筋肉を中心に刺激することです。
② 栄養|栄養補給がなければ筋肉は作れない
筋肉の合成には、刺激だけでなく“栄養”も必要です。
中でもたんぱく質は重要で、体重1kgあたり1.2~1.5g/日が目安とされています【Bauer et al., 2013】。
また、ビタミンDも筋力・バランス機能・転倒予防に関与する栄養素であり、不足しがちな高齢層は積極的に摂取したい成分です。
③日常で“こまめに動く”習慣を持つ
筋トレだけでなく、日常生活の中で 「こまめに動く」こと がサルコペニア予防の要です。
- エレベーターではなく階段を選ぶ
- 買い物や掃除を積極的に行う
- デスクワークの合間に立ち上がり、軽く歩く
こうした小さな行動の積み重ねが筋肉の維持に直結します。
まとめ|筋肉は“老後の保険”である
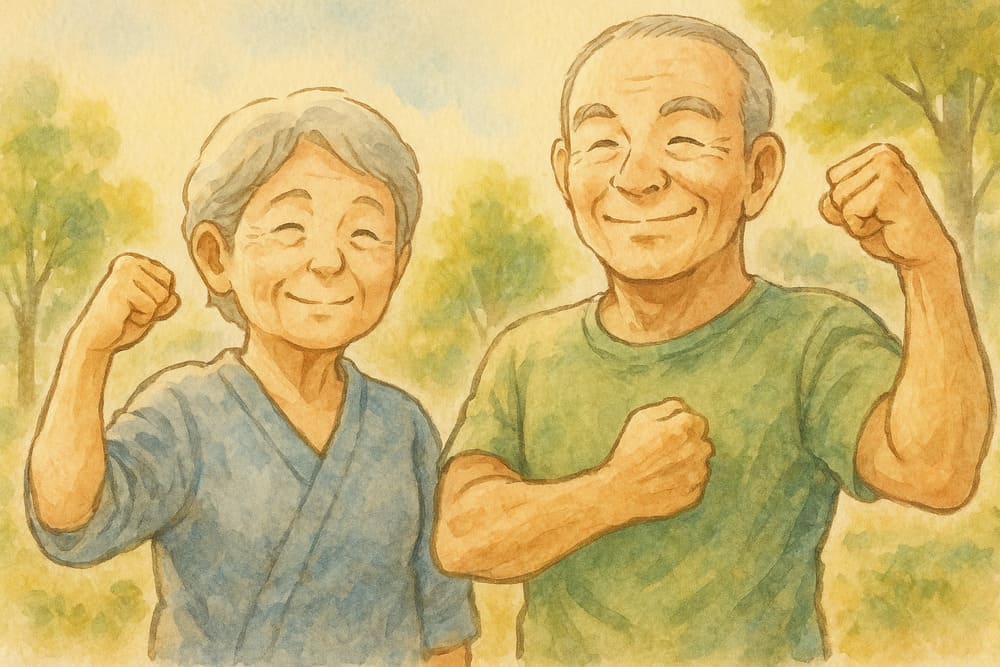
サルコペニアは自然な老化現象に見えますが、運動・栄養・生活習慣によって進行を抑えたり改善することが可能です。
筋肉は一朝一夕ではつきませんが、続けることで「動ける未来」を守る大切な資産になります。
サルコペニア対策は、未来の自分のための“健康投資”です。
今日からできる一歩を踏み出してみましょう。
TYOKUFITであなたに合ったトレーニングを

兵庫県・阪神尼崎駅から徒歩5分のパーソナルジムTYOKUFITでは筋力アップだけでなく、機能改善・健康維持・サルコペニア予防も目的としたプログラムを提供しています。
- パワーリフティング優勝実績のトレーナー監修
- NSCA-CPT資格保持で根拠に基づく運動指導
- 初心者・高齢者・女性の方も安心して通える環境
「自分に合った運動方法がわからない」
「将来の健康を守るために何か始めたい」
そんな方はまずは無料カウンセリンあグへお越しください。
LINEからのご相談や初回体験予約は随時受付中です
参考文献
- Breen L, Phillips SM. (2011). Skeletal muscle protein metabolism in the elderly. Nutr Metab.
- Lexell J et al. (1988). Human aging, muscle mass, and fiber type composition. J Gerontol.
- Narici MV, Maffulli N. (2010). Sarcopenia: mechanisms and significance. Br Med Bull.
- Kortebein P et al. (2007). Functional impact of 10 days of bed rest in healthy older adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci.
- Cruz-Jentoft AJ et al. (2019). Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. Age Ageing.
- Bauer J et al. (2013). Protein intake in older people: recommendations. J Am Med Dir Assoc.

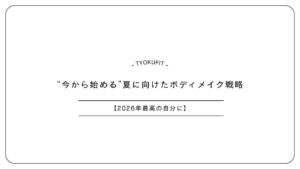

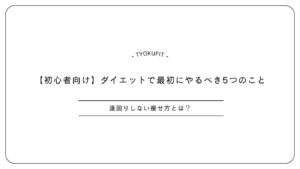
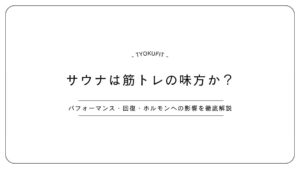
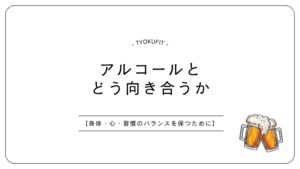
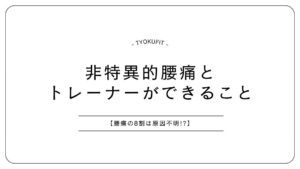


コメント